自閉症の子供と暮らしていると「なんでこんなにこだわるの?」「もう少し融通が利けば…」と思ってしまうことがあります
親であるパパ自身も、Q太郎の行動に戸惑う瞬間は少なくありませんね実際…
けれど、その「こだわり」や「不器用さ」は、本人にとって大切な安心の拠りどころであり、決してわがままではないのです…と感じています
とはいえ、周囲からはどうしてもネガティブに受け取られがちで、誤解や負担が生じることも多々あります
だからこそ、「特性を理解すること=その子を守ること」につながります
本記事では、自閉症の特性をどう捉えるか、そして親としてどんな姿勢で向き合えばよいのかを、パパ自身の体験も交えながら考えてみたいと思います
どっちかと言うと当事者の親は理解していますが、他人の理解はなかなか…ねと言う感じですけども
 QAパパ
QAパパ同じ特性の子を持つ親としては知っておきたいことですね
周りの人で全く知識がない人に特性を理解してもらうっていうのは、結構敷居が高いですねぇ・・・
自閉症のそのこだわりって”わがまま”じゃない?
特性と分かっていてももうちょっとなんとかならんかと思ってしまいますし
融通が利かないっていうのが大きいんでしょうか?
自閉症の子供を育てていると、日々「なんでこんなに融通がきかないんだろう」と思う場面に直面します(毎日ですよ)
親であるパパ自身も「これはわがままなんじゃないか?」と感じてしまう瞬間があるのが正直なところです
たとえば「同じ順番でないと嫌」「予定が変わるとパニックになる」「特定の物に強くこだわる」
―こうした姿は、知らない人から見ると「勝手だな」「自分中心すぎる」と受け止められてしまいがちだと思います
だけど、実際には「わがまま」と「特性」には大きな違いがあることも認識しなければいけません
わがままは「自分の欲を通すため」に行動しますが、自閉症のこだわりは「安心するため」「混乱を防ぐため」に必要とされるものといわれています
つまり、言うなれば本人にとっては生きやすさを守るための「仕組み」なのです
頭では理解していても、親としては「もう少し柔軟になってくれたら楽なのに」と思うこともあります
だからこそ大切なのは、こだわりをただ「ダメ」と押しつぶすのではなく
「これは必要なこと」「でも社会生活で支障が出にくい形にどう調整できるか」と考える視点を大事にします
わがままに見える行動の背景を知ることで、親も周囲の人も少しずつ受け止めやすくなります
・・・とはいえ、自閉症の方の性格上、ここまではワガママ!、ここまでは特性!と言うこともありえます
100%ワガママは特性!ってわけではありません
なので、その点も判断するのは難しいでしょうね
ネガティブにとる理由
自閉症の特性そのもの自体は、もちろん「悪いもの」ではありませんが、受け取る側の立場によってはどうしてもネガティブに映ってしまうことがありますね(残念ながら)
その背景には、その人自身の育ってきた環境や価値観(バックグラウンド)が大きく関わってくるとおもいます
たとえばー
- タイミングを選べない:場の空気に関わらず、自分のペースで行動してしまう
- 度合いが大きい:少しのこだわりではなく、とことん突き詰める形で表れる
- 相手に気を使えない:本人に悪気はなくても、相手から見ると「無視された」と感じてしまう
などなど
こうした行動は、一般的な「協調性」や「思いやり」とは違うため、どうしても「付き合いにくい」「困った子」と見られがちです
さらに、社会全体で自閉症の理解がまだ十分に広まっていないことも大きな要因でしょうね
支援や配慮が前提であるにもかかわらず、その前提を知らない人にとっては「ただの困った行動」に見えてしまいます
だからこそ、周囲の人に「これは特性なんだ」と知ってもらうことが極めて大切になってきます
知識があるだけで見え方は変わったり「迷惑」ではなく「仕方ないこと、工夫すれば一緒にやれること」へと受け止め方が変わっていけると思います
問題がないわけではないということ
自閉症の特性を理解することは、もちろん大切なことです
だからといって「すべて問題なし」とは言えませんね
実際には、特性ゆえの行動が周囲に負担をかけたり、生活に支障を生じさせたりする場面は少なくありません
本人が強いこだわりを持っていても、自分で制御できなければ周囲の人がその影響を受けることになります
小さなことなら笑って受け流せるかもしれませんが、度合いが大きくなると家族や学校、地域社会での負担は確実に増えていきます
(まぁ、Q太郎の場合もそうなので、パパママは痛いほどよくわかっています・・・)
「特性だから仕方ない」と理解していても、実際に毎日接する人にとってはストレスがたまるものです。。。これは切実に
親や支援者であっても「これはきついな」と感じることはありまして、でもだからと言って、その正直な感覚を否定する必要はありません
大切なのは、特性を「守るべきもの」として尊重しつつも、同時に「社会で暮らすために必要な調整」があることを忘れないことですね
理解や許容が広がれば生きやすさは増しますが、それでも「全てを許容してもらえるわけではない」という現実があります
その間をどう折り合い、どの部分を工夫していくか―そこが支援や親の役割になるのだと思います
大事なのは特性と言える範囲
自閉症の特性の中でも、とくに「こだわり」は強く表れやすい特徴のひとつです
ただし、そのこだわりがすべて「特性だから仕方ない」とされるわけではありませんということは上記でも言っています
どこまでを「その子らしさ」として受け入れ、どこからは社会生活のために調整が必要なのか
―その線引きがとても大事になってきます
我が息子Q太郎の場合はエレベーターのボタンに強いこだわりを持っています
誰よりも先に押したがるし、気が済むまでボタンを何度も押してしまうこともあります
本人にとっては安心や達成感につながる大切な行為ですが、混雑している時や急いでいる人がいる場面では、周囲に迷惑をかけてしまうこともあります(そういう時はさせないようには教育していますが)
つまり「特性だから全部許される」という考え方だけでは、残念ながら本人も周りも不幸になってしまうのです
大事なのは、こだわりそのものを否定するのではなく、「どういう場面なら問題が少ないか」「どの程度なら周囲も受け入れられるか」を一緒に考えることです
「特性」として認めることと「社会のルールに合わせる工夫」を両立させること
その両立すっっっごい大変なことだと思いますが、そのバランスこそが、本人の生きやすさにも、周囲の安心にもつながっていくことでしょう



カチカチカチ・・・(エレベーターのボタンを連打する音)
市民権を得ることのメリット
自閉症に限らず発達障がいの特徴的に、周囲に知られていないと「変な子」「扱いにくい子」と見られがちです
でも、学校やなにかのコミュニティでの中で一定の認知や理解を得られると、その子供や家族にとって大きな安心につながります
それが、いわば「市民権を得る」ということになります
「自閉症はこういう特性・特徴があるんだ」と広く知られていれば、たとえ奇異に見える行動をとったとしても「あの子はそういう特性なんだな」と受け止めてもらいやすくなります
結果として、冷たい視線を浴びることが減り、本人も周囲も余計なストレスを抱えずに済むと思います
市民権を得ることは、単に「周りに受け入れてもらえる」というだけじゃなく
「周囲にとっても対応の負担が軽くなる」という利点があります
理解がある環境では、本人も無理をせず、周りも過剰に我慢する必要がありません
皆さんも経験あるでしょ?周りに認められるということは居心地がいいし楽でもあることを
理解や配慮の前提が共有されているだけで、余計な誤解や衝突を防げる―これこそが、市民権を得る最大なメリットです!
助かる本人と家族
自閉症の特性が社会に理解され、受け入れられるようになると、いちばん助かるのはやはりご本人とそのご家族です
誤解やトラブルが減るだけで、日常生活のハードルはぐっと下がります
楽になるというか、疲れる機会がグッと減りますね
本人にとっても「なぜ怒られるのか」「なぜ嫌われるのか」がわからないまま傷つく経験が少なくなります
周りから理解を示してもらえることで、自己肯定感も守られ、安心して行動できるようになります
小さな誤解や衝突が減るだけでも、毎日の過ごしやすさは大きく変わるもんです
家族にとっても同じですね
子供の行動を「すみません」「ごめんなさい」と周囲に頭を下げ続けるのは、想像以上に負担が大きいです
しかし、その市民権が広がり「そういう子なんだね」と自然に受け入れてもらえれば、親がその場にいなくても大きなハレーション(衝突)が起きにくくなります
もちろん、家族が常に横にいてサポートできるわけではありませんからね
だからこそ、社会全体…自分の周りだけでもが理解してくれていることが、本人と家族の大きな安心につながります
他人の見方もさることながら…
自閉症は「他人からどう見られるか」という視点で、語られることが多いです
(まぁ、自閉症に限らず発達障がい全般とかもそうですが・・・)
確かに周囲の理解が広がることは本人にとって大きな助けになりますが、実際には他人の見方そのものがそもそも「正しい」かどうかはわかりませんし、他人の視線はどうしても避けられません
むしろ、人によって受け止め方がまったく違うのが現実です
なにも自閉症や発達障がいに限らず、これは対人関係という大きなテーマでの悩みどころだと思います
極端な話をすれば、他人の評価は正解でも不正解でもなく「ただの印象」に過ぎません
だからこそ「どう見られるか」に振り回されすぎるよりも、「できるだけ良く見えるように工夫する」「誤解されにくいように伝える」といったスタンスの方が現実的かもしれませんね
でも、自閉症の子供が自分の力でその道を切り開くのはとても難しいことです
だからこそ、家族や支援者が「誤解を減らすための橋渡し」をしていくことが重要になります
他人の見方を完全にコントロールすることはできませんが、少なくとも「どうすれば伝わりやすいか」を工夫する余地はあるのです
自閉症の特徴として、手をひらひらしたり、体を揺らしたり、奇声を上げるなど、一見無目的に同じ行動を繰り返すことをスタイミング(常同行動)といいます
Q太郎の場合は、奇声というか宇宙語で文句っぽくいうのと、手をこすりますね
現時点はそれを無くしていくために回数を減らすのと、別の行動に置き換えさせようとしています
これらの行動は周りから見るとインパクトが大きいので、より他人の理解が必要になってきます
度合いを小さく、回数を少なく、他の行動に置き換えるなど、今猛烈にがんばっています



スリスリスリ・・・(手をこする音)
でも結局はそのコミュニティ話
「世間は広いし、環境は一つじゃない」ということを声を大きくして言いたいです
学校、地域、職場、友人関係―人はさまざまなコミュニティに属して生きています
そして、その一つひとつの環境によって、特性が受け入れられるかどうかは大きく変わってきます
ある場では「変わった子」と見られてしまうことも、別の場では「個性的で面白い」と受け止められることもあります
結局のところ、「理解してもらえるコミュニティ」に出会えるかどうかが、本人や家族の生きやすさに直結しているのです
だからこそ大切なのは「一つの場ですべてを解決しようとしない」ことだと思いますね
ある場所で受け入れられなくても、別の場所では受け止めてもらえる可能性がある
その事実を知っているだけで、気持ちはずいぶん楽になります
心構えは重要で「ここでは難しいけど、あっちでは大丈夫」
そうやって複数の居場所を持てることが、本人にとっての安心、安全、そして自己肯定感を支える大事なポイントになります
世界は一つじゃない、だからこそ「自分に合うコミュニティ」を見つけていくことが大切ですよ
そういう子供を持つ親として気にしたいこと
自閉症の子供を育てる親として、日々感じるのは「他人ほど無責任な存在はない」ということ
もちろん悪気があるわけではなくても、外から見ている人は自由に意見を言ってきます
「もっとこうすればいいのに」「しつけが足りないのでは」といった言葉を投げかけられることもしばしばありますね
ですが、実際に子供と一緒に過ごし、支え続けるのは親やごく近い家族になります
そこの違いはとても大きいのです
私たち親が気を付けたいのは「どこで、誰と、どう向き合うか」をしっかり意識することです
他人の言葉に過剰に振り回されるのではなく、まずは自分たちのいるコミュニティ―学校、地域、療育の場などで対話を重ね、理解を築いていくことが大切となってきます
上でも既に言っていますが
先回りして「こういう特性があります」と伝えたり、あらかじめ予防線を張っておくことがとても有効で、事前に共有しておけば、いざというときのトラブルも減り、子供も親も安心できます
そして、すべての人に理解してもらうことはできません
でも、少なくとも「子供が安心できる場」「家族が支え合える場」を守ることはできます
そのために、親としてできる工夫と準備を怠らないことが、子供を護り、家族を支える一歩になるのだと思います
まとめ
自閉症の特性は、わがままでも怠けでもなく、その子が安心して生きるために必要な「仕組み」です
ただ、周囲からは理解されにくく、誤解や衝突を招いてしまうことも少なくありません
そのたびに本人も家族も疲れてしまうのが現実です
だからこそ大切なのは、「特性を守る」ことと「社会で折り合いをつける」ことの両立になります
すべてを許容してもらうことはできませんが、理解が広がれば誤解は減り、市民権を得ることで本人も家族も暮らしやすくなります
そして、ひとつの世界にこだわらず、複数のコミュニティに居場所をつくることで、生きやすさはぐんと広がることでしょう
親としてできるのは、子供の特性を否定せずに守りながら、周囲とつながり、必要なときには予防線を張っておくことです
他人の言葉に振り回されすぎず、自分たちのペースで環境を整えていく―その積み重ねこそが、子供にとっても家族にとっても安心できる未来につながるのだと思います



当の本人にも市民権を得てもらうために頑張ってもらうのは当然ですが、すぐ限界を迎えると思います!
でも、パパママの親視点で言うと、子供を介していろいろな人との出会いが多いと思います
そこでの学びやいろいろな人とつながっていくのがまずは最初の一歩かな~と思います
ゆっくりでいいと思うんですよ人と距離を詰めるのは



でも、パパあんましゃべんないじゃん
黙ってると感じ悪いし



・・・・・
——————————————————-
QAパパの楽天ROOM
療育グッズも載せてるよ
【あわせて読みたい】
自閉症とわかるまで
第1回
【period0-1】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで
第2回
【period0-2】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで (検査施設に行った編)
第3回
【period0-3】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで (検査結果編)
第4回
【period0-4】 自閉スペクトラム症とわかってから (幼稚園に報告編)
第5回
【period0-5】 自閉スペクトラム症とわかってから (ママの勉強編)
第6回
【period0-6】 自閉スペクトラム症とわかってから (療育編)
第7回
【period0-7】 自閉スペクトラム症とわかってから (年齢別詳細)
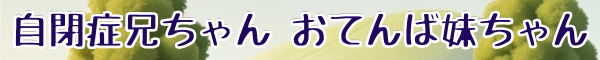


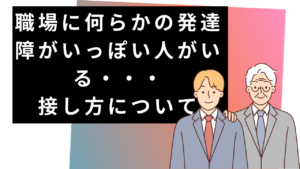

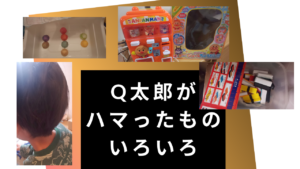



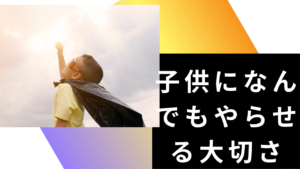

コメント