子供をもつと「学校に行きたくない~」っていう場面にしばしば直面すると思います
まぁ、誰でも億劫になるときはあるでしょ?
子供の取り巻く環境もそうですが、子供なんて遊びたいさぼりたいって言うのはあると思います
あとは純粋に休みたいとかですかね
もちろん、中には深刻な原因もあると思いますけど・・・
そんなわけで
子供の状況によりますが、学校に行かせるコツみたいなのを紹介していきますので、一助になればと
ただ、無理は禁物ですよ
あくまでも子供のペースで・・・と言うことが重要です
原因を考えてみる
物事には必ず理由があります
そして、行動にも理由があって、学校行かない理由というか、原因があります
最近は「学校行くことが当たり前」って言う考え自体変わってきて
「別に学校行かなくてもいいんじゃね?」っていう親御さんも増えてきてるのも事実です
ただ、学校行くことに疑問を感じないとしても、何かが原因で学校に行かなくなってしまうことは問題だと思います
初めから考えがあって学校行かないのなら、まだいいんですけどね
そうじゃないから困るんです
以下に何パターンかその理由をあげてみます
長めの休み明けだとつらい
特に休み明けだと、学校に行くのが少し重く感じることもあります
まず、学校に行くことを無理にすすめるよりも、子供の気持ちに寄り添ってあげることを優先しましょうか
例えば「今日はどんな気持ちなのかな?」「少しだけ頑張ってみる?」とやさしく話しかけてみましょう
また、「最初はちょっと大変でも、先生や友だちに会えると気持ちが楽になるかもね」と、行くことで楽しいことや安心できることがあることをイメージさせるのもいいですね
一緒に朝のルーティンを工夫したり、気持ちが和らぐような「学校行く前の楽しみ」を見つけるのもおすすめな方法です
人間関係
お子さんが人間関係で悩んでいると感じると、親としても心が痛みますね
やさしく寄り添いながら、こんなふうに話してみてはいかがでしょうか
「学校で何か心配なことがあるのかな?」と、まずはお子さんの気持ちを聴いてみる姿勢を見せると、少しずつ話してくれるかもしれません
「友だちと合わないことがあっても、毎日少しずつ違うことを見つけてみようね」や「無理に仲良くならなくても、自然に合う友だちがきっといるよ」と、焦らず見守っていることを伝えると安心できるかもしれません
また「いつでも家で応援してるからね」と、家が安心できる場所だと伝えてあげることも、心の支えになりますね!
なんとなくアンニュイ
お子さんが「なんとなくアンニュイ(倦怠感、憂鬱)」な感じで学校に行きたがらない時って、大人も一緒で、同じ状態になるときがあります
そして、この状態って説明がつかないときありますけど、まぁ共感できるんじゃないでしょうか(笑)
こんなときは「無理に理由を考えなくてもいいんだよ」と伝えてあげるのもいいかもしれません「時々、何も理由がないのにやる気がでなかったり、学校に行きたくなかったりすることってあるよね」と共感してあげると、少しほっとするかもしれません
「今日はできることから少しずつやってみようか?」と、無理なくできることを一緒に考えてみるのもいいです
そして「どんな気持ちでも、パパやママはいつでもそばにいるから安心してね」と伝えることで、お子さんが自分のペースで心を整えられるようになれるかもですね
疲れるので今日はお休み
お子さんが「疲れるので今日はお休み…」となんとなく休みたがる時は、優しく話を聞きながらお子さんの気持ちに寄り添っておきましょうか
まず「最近、少し疲れちゃってるのかな?たまにはゆっくり休むのも大事だね」と、気持ちを受け止めてあげましょう
そうすることで、無理せず安心して自分の状態を表現できるようになります
「明日は元気に学校に行けるように、今日は心も体もゆっくり休もうか?」と声をかけて、リラックスできる一日を作ってあげるのも一つの方法です
「少しずつでも前に進めれば大丈夫!」と伝えると、お子さんも「明日は頑張ろうかな」と思えるかもしれません
全体を通して、言えることは
頭ごなしに「学校に行きなさい」は極力しないで
学校に行かない(行きたくない)理由を聞くことですね
誰でもそういう時がある
・・・って言うの理解してほしい
もちろん、周りの人がね
誰でもいつだって”やらなくてはいけないこと”をやりたくないときはある
なので、その気持ちを無理なく反転させることが一番大事になってきます
我が家のケースは
我が家はそんな切羽詰まった状態ではありませんが、アンテナ高めに子供の状態を頻繁に見ています
Q太郎はASDなので、それ相応の特性がありそうですが、今のところ学校行きたくないっていうことはなく、平穏無事ですね
むしろあんちゃんのほうが…
 アンちゃん
アンちゃん・・・



パパも子供の時は、学校ずる休み何回かしたけども
家にいてもやることないんだよね
睡眠時間も足りてたんで、2度寝するわけでもないので
暇だったな
アンちゃんのケース
まだ、小学校低学年なんで、明確な理由は無いとは思っていますが
普段から学校の人間関係や「いじめはある?」みたいな直な質問ももちろんしません(笑)
いじめって、本人が認定しない場合もあるし、認定したくない場合もあるので
まずは極力その言葉を使わないようにします
その子供の取り巻く環境やどんな人間関係
そして一番大事なのは他人が自分の子に対してどんな言動をとってるかです
いじめっ子を把握することも大事ですが、まずは自分の子供がないがしろにされてないかのチェックから始めます
いじめって、エスカレートするもので
どんどん大きくなればなるほど、どんな状況で隠ぺいしようとしても、子供の話を外側からうっすら聞くだけでも違和感を感じる可能性が高くなります
まぁ、エスカレートする前に片付けるのが一番スムーズな解決対応ですけどね
いずれにしろ、子供の細かい動向チェックはしておくべきです
パパはこれ親の義務・責務だと思っています
話戻ってアンちゃんですが
・・・アンちゃんの性格的に強く言われるのは嫌みたいで
そして、今の友達グループはそういう子いない
なので、学校たまに休む理由は、ただただ億劫だから(・・・のようです)
そして、月曜日に休むことが多い・・・
もうこれQED(証明完了)だろ(億劫だから)
・・・とはいえ、油断しないで子供の動向はじっくり探っていきたい



昨日一日休んで学校行ったけど、勉強どうだった?
アンちゃんが休んでも授業進むわけだから
わからなかったところなかった?



たしかに・・・
今日算数で掛け算3の段やってた
2の段やったの知らない・・・



ほら、ごらんなさい!!
休んだ分教科書読み直してみて
休むとこういうことが起きるから大変なの



休むとその分置いて行かれるからめんどくさいんや!
一方Q太郎は??
Q太郎はその特性がマッチしているのかどうかわからんのですけども
学校行くのが完全に日課になっています
むしろ体調不良でも学校行こうとするので、完全にアンちゃんの真逆ですね



学校行く~♪
人間関係的には
Q太郎にちょっかい出す子はいるだろうし、面と向かって悪口言う子ももちろんいるでしょうけど、Q太郎があんまり感じない(感じないというより認知しないという言い方が正しいですが)というのも学校に行く追い風かもしれませんね
まぁ、人間関係については普通のケースとはかなり違うだろうし、あとついてくれる先生もいるので、直接的なものは今のところほとんどないと思っています
先生方も学校の環境を良くしてくださって、他の生徒たちもQ太郎に気をかけてくれています
子供が学校に行きたがるって言うのは、こういう環境構築がとても大事で、常日頃から周りの人が努力してるってことですね
そういうこともあって、Q太郎は「学校行きたくないとき」がほとんどないのです
まぁ、Q太郎の将来はいろいろと不安ですけど、小学校に関しては親としてはまずは安心ですね
解決策いろいろ
さて、ここからは学校に行くための方法ですかね
学校に行きたくない・行かないと言うところからの解決策となります
まず、当たり前ですけど、原因の究明です
これは普段から子供とのコミュニケーションとってれば、問題解決が近くなると思います
また、学校の先生へ普段の子供の様子やお話を聞いてみるといいと思います
先ほど、Q太郎のとき話しましたけど、やはり「環境づくり」はとても大事で
子供が学校へ行きやすい環境作りを目指しましょう
具体的には、その子その子に合ったものがあるので、確実なものはないものの・・・
学校行かなくちゃいけないという危機感を煽るのは割とNGで、ある程度成熟してるのならいいですけど、責任感・義務感を強く意識させることは、プレッシャーを感じやすくなるような気がします
というか、子供の時はのびのびやってほしいので、希望をあたえるようにガイドします
明るい未来を想像させてください
ポジティブな言葉かけです
例えば「学校に行けば新しい発見や、楽しい友達と出会えるかもね」と、学校でのポジティブな可能性に焦点を当てて話します
「今日は何か一つでも楽しいことを見つけてみようか?」と、小さな目標を与えることも有効で
のびのびした気持ちで学校生活に臨めるように誘ってあげましょう
「どんなことでも、失敗してもいいんだよ。今日はできるところまでで大丈夫だからね」と、無理に完璧を求めない姿勢を伝えるます
これが大事で、安心して学校に行けるようになるかもしれませんね
あとは、いろいろなタイプの「友達」を作っておくことが大事で
友達の人数が少ないと、その子が休んだり、ちょっと仲が悪くなったときには途端に学校へいきたくなくなるとおもいます
きつめの言い方をすれば、相手に対しての依存度が強くなりやすいので、人数を増やし分散することを意識した方がいいかもしれません
他にもいろいろありますが、難易度が高くなってくる…と言うよりかは、がんばって身に付けなければいけないスキルなので、ここからは箇条書きにさせていただきます
- <トラブル回避力を上げる>
トラブル起きる前に気付けばいいですけど、常にトラブル回避をうかがうのは、ある意味気を使い消耗することになるので、やりすぎはNG
子供に気を張って疲れるようなことはさせたくありません(パパ持論)
でも、トラブル回避力と言うのは重要なの
妄想力たくましい人は常にIFを考えて頭の中でトラブルシミュレーションするか
いろいろな経験談・失敗談を聞いておくか、実際に体験するか(泣)しかありません
そもそものトラブル自体が起こさないようにする無難な立ち回りを習得しておくことも大事です
トラブルと言えば、やっぱり人間関係が一番多いと思うので
問題ある子に近づかないようにして、仲良い友達を複数作っておくことをおすすめします
- <自分の中(気持ちや考え方)で対応>
相手に問題があるとき、悪い時
それは相手に改善してもらうことが筋でしょうが、そうもいかない悲しい事実もあります
いろいろ理由がありますが、相手の「悪い」が表沙汰になっていないとき
相手に注意ができないとき 相手がモンスターすぎる場合
こういったケースは悪い方が改善しない場合があります
まぁ、普通にそういう相手は距離をあけた方がいいです
自分がとばっちり食う可能性があるので、それが最善策です
そしてもう一つは自分の気持ちや考え方を変えることです
極端な話、嫌なことがあっても嫌と感じなければいいのです
「これはしょうがいない」とおもうことや、諦めに似た感情・・・気持ちの切り替えって言った方が前向きですが(笑)
それができればいいですね
嫌だと思うことを好きだと思うことが最強ですが、そんな人はなかなかいないので、嫌なことを嫌な気持ちになりにくくするのがまずは目的とするといいでしょう
最終的には嫌なことを嫌と感じないことですかね
でも、これは大人になっても難しいので、無理せずゆっくりじっくりやってもらうことになると思います
他にも、心構えを言うといくつかあります
鈍感力ましましにして、心頭滅却すれば火もまた涼し・・・要は嫌ことに対して鈍感になることです
他にも疲れないような心構えとして、常にポジティブになることもありですね
急は無理でも、ちょっとずつ~やっていく感じです
最後に~学校に行くコツ~
上でも話しましたけど、やっぱり学校行く一番の理想は行きたくない原因を解決することです
でも、そういうのも難しいときもありますし
そして、原因がないのにちょっとでも学校行くのが嫌だったら、その気持ちを押し殺して、登校を習慣化したり、否が応でも体が準備するような状態に作りたいですね
自分じゃなく子供のことになるから、子供の気持ちに寄り添った対策をするのが親としてのベストな対応策だとおもいます



その子の取り巻く状況的に学校に行くということが必ずしも最良の選択にならない場合もあります
まずは、家族会議して、納得できる方針を決めたいですね
——————————————————-
QAパパの楽天ROOM
療育グッズも載せてるよ
【あわせて読みたい】
自閉症とわかるまで
第1回
【period0-1】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで
第2回
【period0-2】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで (検査施設に行った編)
第3回
【period0-3】 自閉症(自閉スペクトラム症)とわかるまで (検査結果編)
第4回
【period0-4】 自閉スペクトラム症とわかってから (幼稚園に報告編)
第5回
【period0-5】 自閉スペクトラム症とわかってから (ママの勉強編)
第6回
【period0-6】 自閉スペクトラム症とわかってから (療育編)
第7回
【period0-7】 自閉スペクトラム症とわかってから (年齢別詳細)
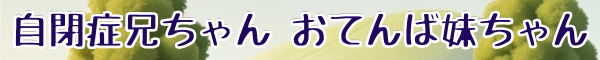
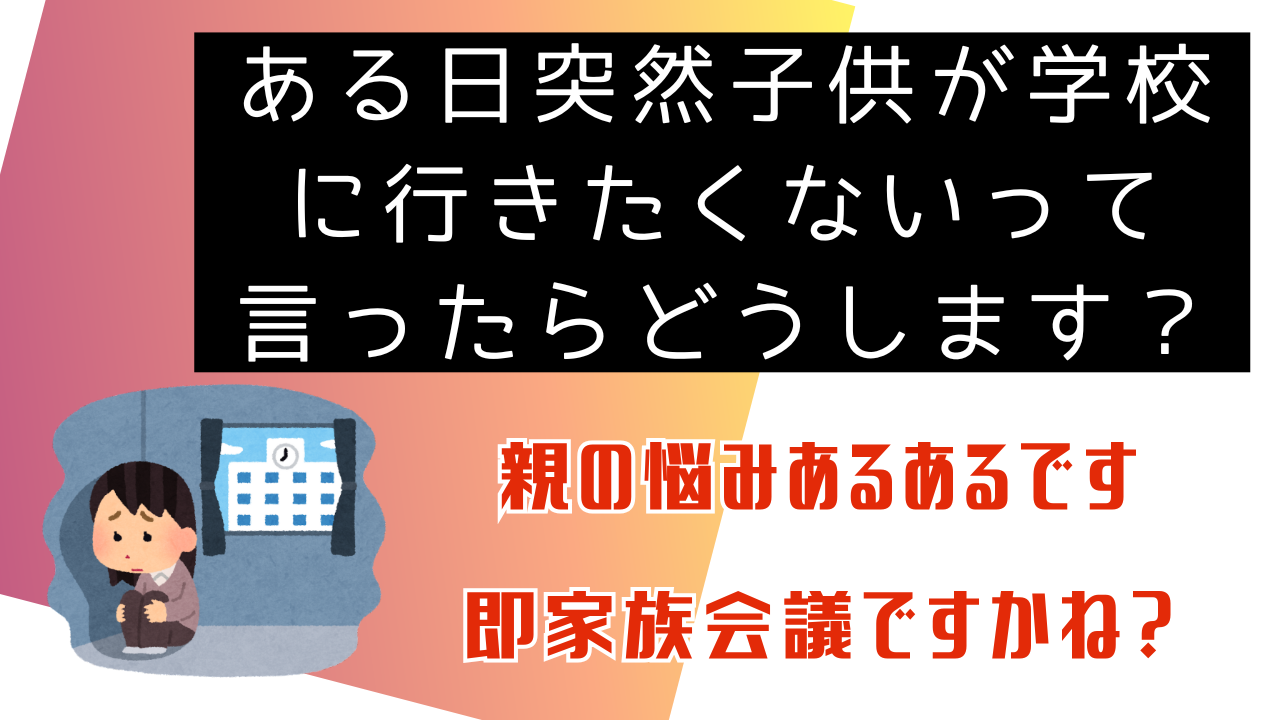


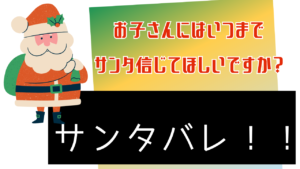
疲れに対してできること-300x169.png)



コメント